桜エビを知る
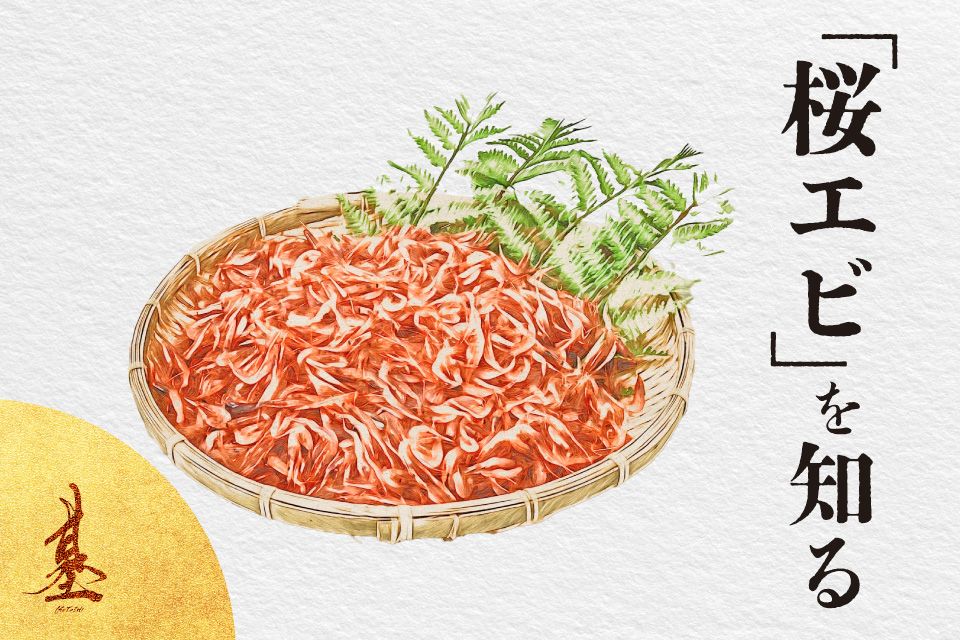
春の味覚「桜エビ」— 小さなエビに詰まった大きな魅力
春の訪れとともに、食卓に彩りを添えてくれる食材の一つが「桜エビ」です。桜の花が咲くころに旬を迎えることからその名がついたとも言われるこの小さなエビは、独特の甘みと香ばしい風味が特徴で、春の味覚として親しまれています。
実は桜エビはいくつかの海域に生息していますが、日本では駿河湾(由比、大井川漁港)のみ漁獲対象となっています。
静岡市にある「由比」漁港は特に桜エビの水揚げ漁港として有名ですが、鎌倉市の「由比ヶ浜」と混同しやすいですね。いつも間違えてしまいます。
さて、今回は桜エビの魅力について、産地や漁の方法、美味しい食べ方などを交えながらご紹介します。
桜エビとは?
桜エビは、体長4~5cmほどの小さなエビで、透明感のあるピンク色が特徴です。生の状態ではやわらかく、繊細な甘みがありますが、加熱すると香ばしさが際立ちます。
桜エビは世界的に見ても生息域が限られており、日本では静岡県の駿河湾が唯一の漁場です。この湾は深さが約2500メートルもあり、栄養豊富な海流が流れ込むため、多くの魚介類が生息しています。桜エビもその恩恵を受け、良質なプランクトンを食べながら成長します。
台湾産の桜エビ(冷凍)を仕入れたことがありますが、色味も味も国産にやや劣る印象でした。加熱する場合にはそう差を感じませんが、生食するにはやはり国産の桜エビが優れている印象を受けます。
桜エビの漁と旬
桜エビの漁は年間を通じて行われているわけではなく、春と秋の二回のみ解禁されます。
- 春漁(3月下旬~6月上旬)
- 秋漁(10月下旬~12月下旬)
特に春漁の時期は、産卵を迎える前の桜エビが最も美味しいとされています。
船曳網漁とは
桜エビ漁には「船曳網(ふなびきあみ)」という独特の漁法が用いられます。これは、夜間に二艘の漁船が協力し合いながら、(もしくは一艘で)海中に網を曳いて桜エビをすくい取る方法です。
許可を受ける船の数は決まっており、漁期や漁獲量などが厳格に管理されている食材です。
夜になると桜エビは群れを作って海面近くに浮上してくるため、これを狙って漁が行われます。船曳網漁は、駿河湾の桜エビ漁で伝統的に使われてきた手法で、エビを傷つけにくく、鮮度を保ったまま漁獲できるのが特徴です。
桜エビの食べ方
桜エビは、生のまま楽しむこともできますが、乾燥させたり加熱したりすることで、また違った美味しさを引き出すことができます。以下に代表的な食べ方をご紹介します。
1. 生桜エビ
春漁の時期だけ味わえる希少な食べ方です。鮮度が良いものは透き通ったピンク色をしており、口に入れるとほんのり甘みが広がります。刺身や軍艦巻きとして食べるのが定番ですが、少量の醤油をたらしてご飯にのせる「桜エビ丼」も絶品です。
2. 釜揚げ桜エビ
獲れたての桜エビを塩茹でして仕上げたものです。ふわふわとした食感が特徴で、ご飯に混ぜたり、サラダにトッピングしたりと幅広く活用できます。優しい味わいなので、お子様やご年配の方にも人気です。
3. 干し桜エビ
桜エビを天日干しにすることで、旨みが凝縮され、独特の香ばしさが生まれます。保存性が高く、一年中楽しめるのも魅力です。お好み焼きや炊き込みご飯、パスタのトッピングとしても相性抜群です。
4. 桜エビのかき揚げ
桜エビの甘みと香ばしさを最大限に引き出せる料理の一つが「かき揚げ」です。薄く衣をまとわせてサクッと揚げることで、桜エビの風味が際立ちます。うどんや蕎麦と合わせると、春らしい一品になります。
5. 桜エビの炊き込みご飯
干し桜エビを使うと、炊飯中にエビの出汁が染み込み、ご飯全体に香ばしい風味が広がります。シンプルに醤油と酒で味付けするだけでも、桜エビの旨みをしっかり感じられる炊き込みご飯が完成します。
桜エビの栄養価
桜エビは、美味しいだけでなく、栄養価も非常に高い食材です。
- カルシウムが豊富:小さな体の中に、牛乳と同等のカルシウムが含まれています。骨の健康を保つのに役立つため、成長期の子どもや高齢者にもおすすめです。
- アスタキサンチンが含まれる:桜エビのピンク色の成分である「アスタキサンチン」は、強い抗酸化作用を持つことで知られています。紫外線やストレスによる体の酸化を防ぎ、美容や健康維持に貢献します。
- 高タンパク・低脂肪:タンパク質が豊富で、しかも脂質が少ないため、ダイエット中の方にも適した食材です。
桜エビを知る|まとめ
桜エビは、日本で唯一、駿河湾で漁獲される貴重な海の幸です。その甘みや香ばしさを活かした料理は、どれも春を感じさせる味わいが楽しめます。生で味わうのはもちろん、釜揚げや干し桜エビ、かき揚げなど、さまざまな形で楽しめるのも魅力の一つです。また、栄養価が高く、健康にも良い食材として注目されています。
春の訪れとともに、ぜひ旬の桜エビを味わい、その美味しさを存分に堪能してみてはいかがでしょうか。
この読み物を書いた人

松岡 雄太
1985年生まれ、埼玉県浦和市(現さいたま市)出身。3児の父。15歳の時に地元の鮨屋でアルバイトを始めたことから和食に惹かれ、日本料理の世界へ入り鮨・割烹・懐石の修行を積む。リッツカールトンシンガポールの老舗「白石」などを経て、令和元年に魚菜 基の店主となる。コロナ自粛期間中にソムリエ資格を取得したほどのワイン好き。
魚菜 基のご紹介
その他の読み物(読み物一覧へ)
-
2024.09.26お店のこと
【基の特製おせち|2026年度】ご予約受付開始
-
2024.11.09料理のこと
香箱ガニとは?



